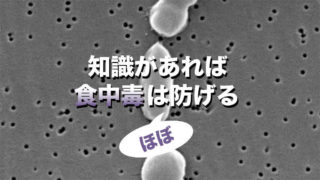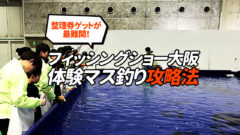色々な情報を集めて釣具を買って釣り場を選んで初めて釣れた魚。最高の瞬間です。
でも釣り上げた魚ってどう扱えばいいのか?どう保管して持ってかえればいいか?とにかく魚を釣りたかったからそこまで調べてなった…
大丈夫。食べるための釣りを専門にしている私が、釣った魚の基本的な処理方法を教えます。
釣って食べるからには命を奪う覚悟を持とう
釣った魚の具体的な処理方法を知る前に少しだけお時間をください。
最初にすることは魚の命を奪うこと
今度はあなたが手を下す番です
例えばスーパーに並んでいる魚や肉などの食材。カニやエビ、貝類を除けば、死んだ状態で売られています。そして死ぬ前までは生きていました。
だから調理されてあなたの口に入るまでにどこかの誰かが何らかの形で手を下しています。つまりその命を奪うという行為をしている。牛も豚も鶏も。そして魚も。
釣った魚を食べるため、今度はあなた自身で手を下す必要があります。
釣った魚に対してあなたがするべき最初のこと。それは魚の命を奪うことです。食べる目的の釣りはそういう趣味だということを覚悟してください。

美味しく食べるための手間は惜しまない
なんていう説教臭いことはこれぐらいにして。
出来るだけ美味しく食べてやろう
つまり何が言いたいかというと「食べるために魚を釣ったからには出来る限り美味しく食べてやるのが責任でありそれが魚へのリスペクトってもんだぜ!」ということを言いたいのです。魚の命を絶つ、つまり魚を締めるということはその責任を果たす第一歩。
可哀そうだと思う気持ちもあるでしょうが必要なこと。我々人間は雑食の生き物。いろいろな命をいただかないと健康に生きていくのが難しい動物です。
今まで意図的に生き物の命を奪うなんてことはしてこなかったはず。でもあなたの代わりに誰かがやってくれていたのです。今度はあなたの番。
食中毒を防いで安全を第一に
締めたあと、死んだ魚をどのように扱うかということはとても重要。それは美味しく、そして食中毒を防ぎ安全に食べるために必要なことです。
食中毒を意識しよう
食中毒は当たり前に起こる
釣った魚で起こりやすい食中毒とそれを回避する方法を知る必要もあります。食中毒の原因となるものは意外なほど日常に溢れています。それは釣った魚とて同じこと。
食中毒の原因となり得る菌や成分は当たり前に魚が持っているものですし、寄生虫は高確率で魚に潜んでいます。面倒くさいこともありますが、手間を惜しまず適切な処理をすれば「安全で美味しい釣りごはん」があなたを待っています。
とりわけ釣った魚で起こりやすい食中毒について記事にまとめていますので、詳しくはこちらをごらんください。
長期熟成にこだわらない
わざわざリスクを高める必要はない
一方で魚の熟成がもてはやされるようになり、それに即した魚の処理方法というものもいろいろと開発されています。YouTubeでは人気コンテンツ。魚の処理にはもはや流派といえるようなものがいくつか存在しています。
確かに目をひきますし、熟成されて旨味が倍増した魚はいかにも美味しそうです。
とはいえ魚を長期保存することは食中毒とのチキンレースとなるリスクを孕んでいます。それを発信する側は経験に基づいた確実な処理をしてると思いますが、それを受け手が安全に再現できるとは限りません。
近頃はサバを1週間寝かせるとかだんだんエクストリームになっていてちょっと心配。
まずは安全確保を第一に
魚の味を楽しめるのも安全が担保されてこそ。
熟成にこだわるのも楽しみの一つですが、まずは食中毒というものが日常的に起こり得るものだと認識する必要があります。熟成させなくたって魚は美味しいですし、新鮮じゃないと味わえない食感というものもあります。
最終的に選ぶのは自分だし責任も自分にある。流されず自らの判断で選択しましょう。
釣った魚を処理する流れと必要な道具
では魚が釣れた直後からなにをすればいいか?順を追って説明します。
魚を釣ってから調理するまでにやること
魚を釣り上げてから、調理する前までにやるべきことを順に列挙してみます。
- 魚から針を外す
- 魚を締める
- 釣り場ではクーラーボックスで冷やして保管する
- 帰り道もしっかり冷やしたまま持ち帰る
- その日のうちに内臓を抜くなどの下処理をする
面倒かもしれませんが、美味しく魚を食べるためには必要な作業です。のちほど一つずつ解説していきます。
釣った魚を持ち帰るために必要な道具
これものちほど流れに沿って説明しますが、魚を安全に持ち帰るためにはこのような道具が必要です。絶対必要な3点をまずはかんたんに紹介します。
- 魚を安全につかむフィッシュグリップ
- 潮氷を作る海水をくむための水くみバケツ
- 魚を冷やして保管するクーラーボックス
安全に魚を掴むためのフィッシュグリップ
鋭いとげや歯を持つ魚は意外と多く、身近に釣れる魚にもたくさん。そこで安全に魚を掴むための道具が必要です。それがフィッシュグリップ。
一般的には必須とされていませんが、安全に楽しく釣りをするために用意して欲しい道具です。
海水を汲むバケツ
こんなもの必要?と思われがちな水汲みバケツも必須。
クーラーで魚を冷やすには海水で満たすのが効率的。その海水はその場で水汲みバケツを使って汲みます。他にも魚を一時的に生かしたり手を洗ったり、釣り場の清掃にも役立ちます。
また、海で釣った魚を新鮮に保存するためには海水が必須。そのためにもバケツが活躍します。
魚を冷やして保管するクーラーボックス
これは説明不要かと思われるクーラーボックス。
釣った魚を持ち帰るなら必ず用意してください。よっぽど近場でない限り、常温で魚を持ち帰るのは危険です。食中毒の危険性が高まるからです。
釣具屋とかで売ってる紐が付いた青い発泡スチロールの箱も、クーラーボックスの代わりとして検討されるかもしれません。
実はへたなクーラーボックスより保冷力が高かったりするのですが、繰り返し長く使い続けるにはちょっと難がありますし意外と高いです。保冷力は落ちますが、まずはホームセンターで買えるような1,000円前後の安いものでも構いませんので必ず用意しましょう。
おすすめは15リットル前後のメーカー製クーラーボックスです。
以上、フィッシュグリップ、水汲みバケツ、クーラーボックスの3点。これは釣った魚を食べるためには必須となるアイテムです。
魚から針を外す方法
さて、最初に釣れた魚はアジでしょうか?イワシでしょうか?
なにはともあれ、落ち着いて魚を針から外しましょう。
糸を張ったまま針を外そうとすると、魚が暴れて手に針を刺してしまう危険があります。慣れないうちは釣り上げた魚を仕掛けごと地面に落としましょう。慌てて竿を踏まないよう気を付けて。
フィッシュグリップがあれば安全で便利
安全に針を外すには、まず生きて動いている魚を固定する必要があります。
もちろん素手でつかんでもいいですが、魚によってはヒレが鋭くて怪我をする場合もあります。魚によってはヒレに毒がある場合もあります。そこで魚をがっちりつかむフィッシュグリップがあると安全というわけです。安全に釣りを楽しむには必須としたいアイテム。
初心者にはワニグリップミニがおすすめ
サビキ釣りで釣りを始めた初心者におすすめするのは第一精工のワニグリップです。
こちらで詳しく説明しているのでご参考に。
このフィッシュグリップで魚のエラを閉じるようにつかむと、たいがいの魚はおとなしくなります。

落ち着いたら魚のどこに針が掛かっているかしっかり確認しましょう。
針を外すためのプライヤーを用意しよう
釣り針は上手くできていて、しっかり針掛かりしていればちょっとやそっとじゃ外れません。単純に引っ張ってもだめ。
針が刺さっている方向をしっかり確認して、針の軸(糸が結んであるほう)を回転させるように針先の向きを変えれば、口の柔らかいアジなどの魚なら簡単に外れます。仕掛けを上げたタイミングでポロポロと針から外れることも多いでしょう。
安全のためにプライヤーを
しかし口の堅い魚や歯が鋭い魚、そして針を飲まれた場合はちょっと面倒。簡単に外れませんし危険なこともあります。そんなときのために釣り専用のプライヤーを用意しておきましょう。
針外しにはノーズが長いタイプがおすすめ。
これで針をつかんで、針先と逆方向に動かせば針を外すことができます。鋭い歯を持つタチウオなんかの針外しにも役立ちます。とりあえず100均で売ってる工具のペンチとかでもいいでしょう。海水に触れるとすぐ錆びますけど。
なお昔から針外しという釣り専用の道具があり針を飲まれた場合などに役立ちます。しかしこれは直感的に使うのが難しく、慣れないとなかなか上手くいきません。
どうしても針が外れない場合は糸を切る
無理に取ろうとせず糸を切る
どうしても針が抜けない掛かり方をしていることもあります。プライヤーが届かない喉の奥に針を飲み込まれた場合など、引っ張っても抜けないことが。
その場合は糸を切るしかありません。仕掛けがもったいないと躊躇しますが、どうしようもないし時間の無駄なのでその場合は潔くハサミで糸を切断しましょう。
もしリリースする場合でも、無理に抜こうと力ずくで針を外すより、針がついたまま糸を切ってリリースするほうが魚の生存確率があがるというのが定説になっています。
まるごと食べるのなら目印を
糸を切った場合はエラや体内に針が残ったままになるので、調理するときは気を付けてください。
例えばアナゴなど、魚種によっては頻繁に針を飲まれる場合があります。その場合は分かりやすいよう、針を飲んだ魚だけ尾びれをハサミで切って目印にするなどすれば調理するときに見分けられて安全です。
大きさによって使い分けたい魚の締め方
針から外れた魚。食べる目的ならすぐさま締めましょう。
食べるなら釣ってすぐに締めるべき
食べるのならスカリはおすすめできない
今まで釣り堀しか行ったことがないのであれば、まずこういったスカリや魚籠(びく)と呼ばれる網で釣った魚を生かすことを思いつくかもしれません。
あるいは水を張ったバケツに入れておくとか。でも安全に美味しく食べるためなら釣れてすぐに締めるのが最適解です。
魚を締めることは美味しさにつながる
締めるということはつまり魚の息の根を絶ち動きを止めること。
より鮮度を保ち美味しく魚を食べるためにはなるべく早く締めることが効果的。そうすることで魚のエネルギー源たるATPの消費を抑えることができるからです。
ATPはバッテリーのようなものだとイメージしてください。通常は魚が呼吸をするなどして充電されるものですが、締めずに魚を動かし続けるとどんどん充電が減っていきます。それを温存するためには強制的に電源を切る、つまり締める必要があります。
ATPは魚の死後に分解されていき、それが魚の旨味のもととなるイノシン酸を生成します。
旨味を残すために
寿司屋にある生け簀をイメージして「美味しく食べるなら調理直前まで活かしておいた方がいいのでは?」という固定観念があるかもしれません。
しかし、死んだ直後の魚はまだATPが旨味成分に変わる前。こういった理由からなるべくATPが残るように早く締めたうえで、イノシン酸が生成されるまでしばらく時間を置いた方が旨味が増える可能性が高まります。
魚の大きさによって最適な締め方が異なりますので、それを見ていきましょう。
とその前に、締めた後に魚を保存する環境を予め整えておく必要があります。
クーラーボックスで潮氷を作っておく
保冷材は冷凍ペットボトルでOK
もちろんクーラーボックスは持ってきてますね?そこには氷や保冷剤も入ってますよね?水を入れて凍らせたペットボトルでもOKです。
後述しますが、保存の際はなるべく海水の塩分濃度を変えない方がいいので、そのままの板氷を使うより保冷材やペットボトルの方が適切です。板氷やロックアイスは、ビニール袋に入って売られているそのままの状態でクーラーに入れたほうがいいでしょう。
潮氷を作っておく
ではそこに海水を注いでください。
まずは氷がひたひたになるぐらいの量を注ぎます。海水は真水より冷えるので-2度程度になるまで凍りません。よって適切に冷えたクーラーボックス内の海水は0度以下の状態になります。
このキンキンに冷えきった海水を「潮氷」と呼びます。潮氷と書いて”しおごおり”と読むのが一般的だと思いますが私も正解が分かりません。塩氷とか海水氷とか冷海水と呼んだりも。
クーラーに入れる海水はその場で水汲みバケツを使って汲みましょう。
水汲みバケツは水を汲む以外にこんな役割を果たします。
- 汚れた手を洗う
- 魚を一時的に活かす
- 魚の血抜きをする
- 釣り場の掃除に使う
- 濡れた小物を収納・運搬する
- アミエビを溶かす
地味ながらとても重要なアイテムといえます。特に堤防釣りをするなら必ず用意してください。これがないとこの記事で書いていることも成り立たなくなります。
サイズによって締め方を変える
作った潮氷の中に入れて釣った魚を保管するわけですが、その前に締める必要があります。釣れた魚のサイズによってどう締めるべきか判断しましょう。おおよその基準と手順がこちら。
20センチ程度を基準に締め方を変える
20センチより小さい魚

生きたままの魚をキンキンに冷えたクーラーボックス内の潮氷に入れて氷締めをする
20センチを超える大きな魚

脳締めと血抜きをして締めてからクーラーボックス内の潮氷に入れて冷やす
それぞれを詳しく見ていきましょう。
なお、この時点で「いちいちめんどくせえな」と思ったあなた。分かります。基本的に私もそうです。そんな場合は、釣れたそばからクーラーボックスの潮氷に放り込むだけでも十分。ちゃんとそれなりに美味しく食べられるはずです。面倒ならすぐ冷やせ。とにかく冷やせ。自分で食べるんならとりあえずそれでOK!
20センチ以下の小魚は氷締めをする
たとえばサビキ釣りで釣れたアジやイワシなど20センチぐらいまでの小魚。釣れるときはひっきりなしに釣れるので、1匹ずつ手作業で締めるのは大変です。
キンキンに冷えた海水に放り込むだけ
ではどうするかというと、クーラーボックスの中でキンキンに冷えた潮氷の中に放り込むだけ。釣ったそばから生きたまま放り込むのです。即死はしないまでも、0度以下の低温でみるみる動きが鈍くなり2~3分も経てば締め完了。たったこれだけです。

この締め方を「氷締め」といいます。
20センチぐらいまでの小魚に関してはこの処理方法がベスト。
小魚は余計なことをせず冷やすだけ
脳締めするとか延髄を切るとか、頭を落とすとか、血抜きをするとか、余計なことをして身の断面を水や空気にさらす方がむしろ鮮度落ちにつながる可能性があります。釣れたら直ちに冷やす、それだけでいい。
なお小魚中心に狙うのであればクーラーの容量は15リットル程度がオススメです。魚はもちろん、レジャー用に使ったりするにもジャストなサイズ。
クーラーボックスに投入口が付いたモデルなら、庫内の温度をなるべく上げずに魚を氷締めさせることができます。
中型から大型魚なら締めて血抜きをする
20センチ以上の大きな魚が釣れた場合、生命力が強く氷締めだけではなかなか絶命に至りません。長い時間、クーラーボックスでバタバタと動いてATPを消費してしまいますし、体をぶつければ内出血したり身割れの原因になったりします。
だからなるべく早く締めて動きを止める必要があります。
脳締めと血ぬきをする
基本はこのような作業になります。
- 脊髄を切ったり脳をピックで刺したりして脳締めをし動きを止める
- エラを切って血抜きをする
- 血が抜けたら直ちに潮氷に入れて冷却する
各工程を詳しくみていきましょう。
大きな魚はまず脳締めをする
残酷な表現になりますが、脊髄、背骨を断ち切ったり、脳を破壊することでそれが可能となります。
ナイフやハサミ、ピックなどを使ってそれをすることになります。もし道具が無い場合、例えば30センチ台のサバであれば頭を背中側にぐっと折り曲げる、いわゆる「鯖折り」をすることで簡単に背骨が折れて締めることができ同時に血抜きもできます。

ただ首を折ることで身も割れて断面が水に触れることになるので、そこから鮮度が落ちたり臭みが回りやすい。気にするほどではないかもしれないですが、個人的にはあまりおすすめはしません。
アイスピックのような鋭利なもので脳を突き刺して破壊するという脳締めがあらゆる魚に有効です。釣り具メーカーから専用のピックも売られています。
百均で売ってるような千枚通しやアイスピックでも代用可能。ハサミの刃先でもいける。
そもそも魚の脳ってどこにある?
ではこれでどこを刺せばいいのか?魚の脳ってどこにある?
魚は私達人間と同じ脊椎動物。だから脳は背骨の延長線上にあります。
基本的には魚の体を尾から頭まで貫く側線の下に背骨があると見立てて、その延長線上にある目の後ろ、人間でいうところのこめかみ付近を一突きすれば魚が痙攣した後グタっと脱力して締めたことを確認できます。
魚種によっては締める過程でカパーッと口がゆっくりと開いたり、眼球がぐりぐりと異常な動きをする様子も確認できるはず。

捌いて頭を割ってみると分かりますが、体の大きさに対して魚の脳はとても小さいです。
それゆえ慣れてないと一突きで締めるのは難しい。突いた後にグリグリとかき回すようにピックの先端を動かせばそのうち当たるはずです。残酷に思えますが、そう思うなら早めに締めたほうがいいはず。
血抜きをする方法
大きな魚は血も多いので、可能であれば締めたあとに血抜き処理もしておきましょう。それをすることで臭みを減らしたり、より長い鮮度保持につながります。
血抜きというと大げさなことのように思えますが、基本的には片方のエラの根元付近をハサミやナイフなどで切断し、頭を下にして海水に浸けておくだけである程度抜けていきます。尻尾をもってフリフリすればより効果的。まだ心臓が動いている状態であればそれがポンプの働きをして血が抜けていきます。脳締めをした後でもしばらく心臓は動き続けます。
エラを切る道具がなければエラを指で引っ掛けて千切るだけでもある程度血が抜けますが、タチウオなどの魚はエラに棘状の突起があったりして危ないので気を付けましょう。
血抜きにおいても水くみバケツが役立ちます。

エラを切る道具は料理用のキッチンバサミでOK。刃の間に汚れが溜まりやすいので、刃が分解できるタイプのキッチンバサミがおすすめです。
ダイソーなどの100均で売ってるカニばさみが分解出来て使いやすいです。刃の形状も魚を処理するのにむいています。
もちろん魚を締めるための専用ばさみも有効。
昼間に釣った魚をその夜にすぐ刺身で食べるというなら血抜きを省略する選択も有りかもしれないですし、少しでも長く鮮度を保ちたいのなら血抜きをしたほうがいいかもしれません。血も風味のうちと考えればそんなにこだわらなくてもいいと思うので、各自好きなようにやってください。
血が抜けたらすぐに冷やす
締めて血が抜けたと判断した後はただちに潮氷にいれて冷却しましょう。ダラダラと海水に漬けていたらどんどん鮮度が落ちます。とりわけお湯のように水温の高い真夏は血抜きにこだわるより冷却を優先するべきかもしれません。
なお魚種によっては脳締めをする前に血抜きをしたほうがいい魚もいます。例えばカワハギなどはえらを切って泳がせてから脳締めをしたほうがきれいに血が抜けます。
可能なら釣り場で内臓を抜いておく
血が抜けたらその場で内臓を取る処理をすると鮮度維持、食中毒予防に効果的です。

寄生虫と腐敗の原因は内臓にある
人間に危害を及ぼす寄生虫の多くは内臓に潜んでおり、また魚の腐敗は内臓から始まります。内蔵の腐敗はヒスタミン中毒につながるおそれがあります。そのことから、内臓を取り除くということが食中毒予防と鮮度維持に繋がります。
よほど大きな魚でない限りキッチンバサミひとつあればお腹を開いて内臓を取る処理が可能です。私は20センチ程度のアジでも60センチを超えるメジロでもキッチンバサミ一つで処理します。ナイフもいいですが、思わぬ怪我やあらぬ疑いを避けるためにハサミの方がおすすめです。
抜いた内蔵はその場に捨てない
血や内臓が地面に落ちたら水汲みバケツなどを使って必ず洗い流すようにしてください。釣り場を守る最低限のマナーです。
取り除いた内臓もかつてはその場で海に捨てるということが当たり前に行われていましたが、厳密にいえばこれは不法投棄とみなされる可能性をはらんでいます。コンプライアンスに厳しい昨今、ビニール袋などに密閉して持ち帰るのが無難です。誰が見てるか分かりません。最終的には各個人で判断してねということでお茶を濁したいと思います。
内臓を取り除くのは中型から大型魚に対して有効な処理で、小さな魚に対していちいち一匹ずつ現場で内臓を処理するメリットは少ないと思います。血抜きに関しても同様。やはり小さな魚は氷締めのみでいいでしょう。
一時的に生かしてキープする方法もある
せっかく釣れた魚だけど、サイズが微妙でリリースするか持ち帰るか悩む…
そんなときは一時的に魚を活かしながらキープすることができます。水くみバケツに汲んだ新鮮な海水を用意してそこに魚を放せば、魚種によっては長い時間生かしたままキープすることができます。
魚種によって生かしやすい魚と生かしにくい魚がいる
キープするのに向いている魚はカサゴなどのいわゆる根魚。動きが少なくバケツに入れたままでも長時間活かしたままにできます。大きなサイズが釣れたらキープしていた小さなサイズの魚はリリースしましょう。資源保護のため、成長の遅い根魚の中で特にサイズが小さいものがリリースが望まれます。
反対にすぐ弱ってしまう魚もいて、イワシを始めとする青魚は運動量が多く、ブクブクなどで酸素供給をしないと長いこと生かせません。暑い時期は特に。頻繁に水を換えてやれば長持ちしますが、どんどん泳いでATPを消費してしまうので、持ち帰るならやはりなるべく早く締めたほうがいいです。

暑い時期はヒスタミン中毒の可能性も高まるので、サビキで釣れたサバやイワシを死んだままバケツに放置するのは避けましょう。
大型の魚はタフなので、ストリンガーと呼ばれるキープ用の道具を使って生かすことができます。
大型の魚でもブリやサワラなどの青魚は泳げる環境じゃないとすぐに弱って死ぬことがあります。
魚が死んだままストリンガーにつないで海中保管してる人もいますが、水温が高い時期は味も鮮度もおちるのでおすすめできません。
自分に合ったベストな処理方法を見つけよう
科学的な検証と理屈を詰めていけば、魚種やサイズごとにこれがベストだという処理方法が決められるんじゃないかとは思います。
魚の処理はもはや宗教
しかし血抜きや魚の締め方というものは人それぞれ違った信念があったりあします。ときおりネット上でも論争になるぐらい違う。もはやこれは宗教。本人の意思とは別に教祖みたいな扱いをされてる人もいます。
それでも最終的に自分で「美味しい」と思って食べるのならどれもその人にとっての正解に違いない。だから他人に口出しするのは余計はお世話。自分で考えて適切な処理した結果として美味しいと思ってるのに「そんなの意味ないよ。間違ってるよ。」なんて横から言われたらイラっとくるでしょう。プロならまだしも我々はあくまで趣味として楽しんでるわけですし。
王将が好きでも高級中華が好きでもいいじゃない。インスタントラーメンも人気店のラーメンも美味いよ。食の好みは多様性があるから楽しいんじゃないでしょうか。
自分に合った処理方法をみつけよう
「釣り人は誰より新鮮な魚が食べられる。」
これはその通りなのですが、超新鮮な状態でも時間を置いて寝かせた状態でも完全にコントロール出来て好きに選べるのが釣り人の特権だと思います。
釣ってから調理できるまでの時間なんて人それぞれだし、刺身が好きな人もいれば塩焼きが好きな人もいる。そもそも味の好みなんて違って当たり前なのだから唯一の正解を求める必要はない。
ネットの記事とかYouTubeには魚の処理方法を解説したコンテンツがたくさんあり、確かに理にかなってるなと納得できるものも多いと思います。それが正解だとして再現しようとするのもいいですが、その手間と結果がつり合うのかを考えてどうするか自分で決めればいいのではないでしょうか?
処理方法のこだわりが先鋭化した結果として、青魚を生のまま7日寝かすとかいうエクストリームなコンテンツも見るようになりました。そりゃそれをすすめるあなたは適切なツールで適切な処理をして適切な保存をしてるんだろうけど、それを家庭で完全再現できる保証はないわけで。危ういことしてるなと思います。
ごく普通の締め方をしても、釣った翌日でも十分美味しいのに。
食中毒対策のため冷やして保存するのは大前提で
ということで、締め方や血抜きはいろいろ試してそれぞれ自分にベストなやり方を見つけてください。それがあなたの正解です。
面倒ならとりあえず冷やせ!
しかしそれ以前に食中毒を回避して安全を担保することは必須です。
釣った魚は調理直前までしっかり冷やして保存する。とにかく冷やす。血抜きとか締めとかが面倒ならつべこべ言わずすぐに冷やしておく。食中毒対策のためにこれだけは必ず行ってください。
釣れた魚が死んでいるのにバケツに入れっぱなしだったり、ベテランでも青魚をストリンガーに繋いで死んだ状態で海中に長時間保管している人もいます。確実に食中毒の可能性が高まりますし、美味しく食べるという目的ならもったいないこと。食べるならすぐ冷やせ。とにかく冷やせ。
冷やさない状態の保存だと、ヒスタミン中毒、腸炎ビブリオによる食中毒になる可能性が高まります。魚の味を楽しむのも安全があってこそです。
釣り場から家までの持ち帰り方
氷が溶けそうなら追加する
時間いっぱい。釣りは終了です。大漁だったでしょうか?貧果だったでしょうか?
クーラーボックスの中で最初に作った潮氷は0度前後になり、手を入れたら痛いぐらい冷えています。そして釣った魚もクーラーボックスの中でしっかり冷えているはずです。場合によっては死後硬直でカチカチになっているかもしれません。
残った氷の量を確認して、家まで冷却がもたないようなら追加しましょう。コンビニのロックアイスでも問題ありません。開封せずに袋ごと入れましょう。
クーラーボックス内の海水は捨ててもそのままでも
潮氷を作るためにクーラーに入れた海水はそのままで構いません。
クーラーボックスの海水は釣りが終わったら捨てないと魚が水っぽくなるという定説がありますが、もっぱら海水を入れたまま持ち帰る派の私はそんな風に感じたことはありません。あんまり気にしなくていいと思います。その日のうちに下処理するなら。
頭を落とすなど何かしら加工をして身の断面が直接水に触れる状態なら考えたほうがいいですが。大量に氷が溶けて塩分濃度が下がってる場合はぬいたほうがいいかも。
店頭で売られているサンマなどは、そのように冷たい塩水に漬けられて売られているのを見たことがあるはずです。もしそれで水っぽくなるというなら、魚屋さんはそんな売り方をしていないでしょう。
ただし塩分が一切含まれていない真水で冷やした場合は、浸透圧の関係で魚の身が水分を取り込んで水っぽくなる可能性があります。魚の体液の塩分濃度は人間とほとんどおなじ0.9%。生きてるうちはこれを保つ調節機能がありますがもちろん死んだら失われます。
真水の氷を使うと海水が薄まり塩分濃度が下がるので、氷をビニール袋に入れるなどしておいた方が安心です。

その日のうちに内臓処理などの下処理をする
釣りをしてから帰宅すると、暑い時期ならクタクタに疲れてるはず。
ああ疲れたこのまま風呂に入ってクーラーの効いた部屋で寝たい…という気持ちは一旦置いといて、なるべく当日中に内臓を抜くなどの下処理を済ませておきたいものです。クーラーボックスで冷やしているとはいえど、鮮度は確実に落ちていきます。
早め処理が安全と美味しさにつながる
食中毒予防と臭みの低減、そして美味しく食べるためには早めの内臓処理が効果的です。
内臓を抜く、水分を除去するなどの下処理が済めば、あとは冷蔵庫で保存できます。
ここまでくればあとは煮るなり焼くなり揚げるなり。お好きな調理でお召し上がりください。
魚種にもよりますが、しっかり処理をして適切に冷蔵保存した魚は、刺身で食べられるぐらいの鮮度を2~3日程度問題なくキープできます。
出来る限り美味しく安全に食べるための努力を
釣った魚を持ち帰るまでの流れを解説しました。
魚種によっては、釣り人の間で「臭くて食えたもんじゃない」とされている魚がいたります。湾奥で釣れるクロダイとかスズキとか。もちろん時期や場所によってはその通りになることもありますが、これは釣ってからの処理に左右されるところも大きい。
なるべく早く締めて、大きな魚であれば血を抜いて、帰ったら迅速に内臓を処理する。調理するときも、工程ごとにしっかりまな板を洗い、冷蔵保存する前に魚の水分をしっかり除去する。こうすれば、ほとんどの魚は美味しく食べられます。
美味しく、そして食中毒を避けて安全に食べるための努力を惜しまず、適切な処理をしましょう!