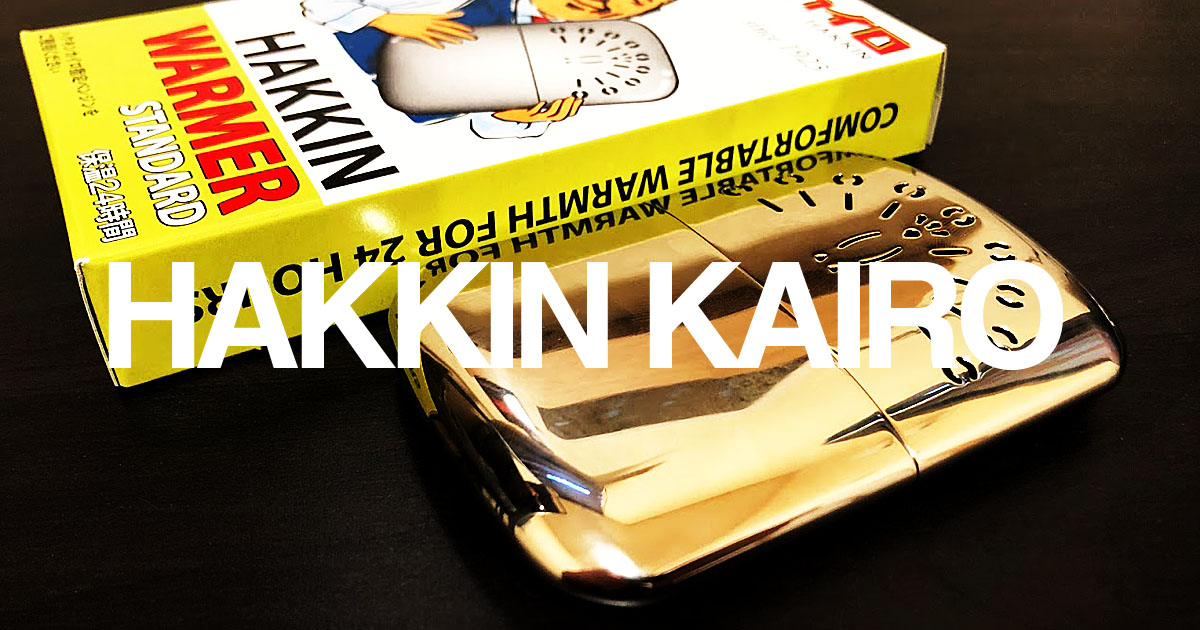屋外メダカビオトープはメダカを飼うという本来の目的とともに「水草を育てる」という楽しみ方も持ち合わせています。
きれいな花が咲く水草だったり、かわいい浮草だったり、和の趣を演出する繊細な水草だったり。メダカの品種おなじく選択肢が豊富です。
そんな水草についての基礎と、初心者でもかんたんで扱いやすい入門用のおすすめ水草を紹介します。
買った水草は放流するな!流出させるな!
どこでも簡単に爆増してしまう
市販の水草はほとんどが外来種
最初にこれだけは知っておいてください。市販されている水草のほとんどが外来種だということを。
夏になると爆発的に増える
例えばホテイアオイ。和風の名前がついていますが南米出身バリバリの外来種。
夏ともなれば爆発的に増えてメダカビオトープの水面を覆いつくします。自然に放流しても同じことが起こる。
川や池の水面を塞いだホテイアオイは日光を遮断し、もともとそこに生えていた在来の水草を枯らしてしまいます。環境のバランスを崩し、そこにいた生き物全般に悪影響を与えます。

逸出対策を徹底しよう
枯らせてから捨てる
あなたのビオトープで増えすぎた水草は水から取り出して枯らせましょう。枯らしてしまえば増殖能力を失います。あとは燃えるゴミにでも出せば問題ありません。
大雨で流出させない
流出しやすい浮草は特に注意が必要。道路沿いの側溝に流れた水がそのまま河川に放水される可能性を想定して、大雨で溢れても安全なビオトープの置き場所を考えるべき。
ホテイアオイやナガエツルノゲイトウなど、侵略的な水草の流出は大きな問題になっています。あなたが作ったビオトープの環境からいかなる生物も逸出させてはならない。これを肝に銘じたうえで水草を楽しみましょう。
ビオトープにおける水草の役割
水草はビオトープに華やかさを添えるだけではなく、メダカ飼育にとっていろいろなメリットがあります。例えばこんな効果が。
- 水を浄化して環境を整える
- 鑑賞用としてビオトープに彩りをそえる
- 光合成をして酸素を供給する
- 日陰を作って水温上昇をおさえる
- メダカの産卵床になる
- メダカの隠れ家になる
特にビオトープ内での水質浄化サイクルを成立させるために必要不可欠なもの。水草を入れることで水換え不要な環境を成立させることが出来ます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
まずはこの2種を導入しよう
ホテイアオイとマツモさえあれば大丈夫
この2種で飼育と繁殖が安定する
メダカ用水草の選択肢はたくさんありますが、迷ったらまずはこの2種だけ導入すれば大丈夫という水草があります。それはホテイアオイとマツモ。


最初はこれだけあれば安定した飼育と繁殖が成立する。この2種について詳しく解説しています。
ビオトープで使える水草を勝手に分類する
独自に4タイプの分類をしました
特長で分けた4タイプ
水草は大きなくくりで水生植物と呼ばれ、その生態や生えている場所によって沈水性や抽水性などのカテゴリーに分類されます。本来ならそのような用語を使うべきですが、これがいまいち覚えにくい。
ここでは私が勝手に分類した4タイプに分けて水草を紹介します。その4タイプがこちら。

- 水面にプカプカと浮くタイプの水草
- 水中にユラユラと漂うタイプの水草
- 水面直下の土に植えるタイプの水草
- 土に植えて完全に沈めるタイプの水草
ほとんどの水草はこの4タイプに分類できます。
水面に浮くタイプの水草
水面に浮くタイプのメリットデメリット
簡単に増やせる
水草の中でも一般的には「浮草」として知られている水草。水面下に根っこがあるものの通常は底に定着せず、風の吹くまま水面をプカプカと浮いています。
いちばんのメリットは増やすのがかんたんなこと。暖かくなればクローンが増殖するかのように倍々に増えるのが特徴です。
水面を覆うように増えるので直射日光を遮って水温上昇を防ぐ効果が期待でき、産卵床として使える水草も多い。初心者が最も扱いやすい水草です。
間引きの手間がかかり越冬させにくい
デメリットはかんたんに増えすぎるから夏場は定期的な間引きが必要なこと。一方で寒さには弱く、日本の冬を超えられるかどうかが微妙なものが多い。
ホテイアオイ
メダカビオトープ界の万能選手
ホテイアオイはメダカ用水草の大定番。水質浄化も産卵床もハイレベルでこなす万能選手。

最初はとりあえずホテイアオイ。迷ったらとりあずホテイアオイ。それが正解です。
冬の寒さに弱い
屋外で冬が超えられるかというと地方によりますが、条件が整えば僅かな緑色の部分を春まで残しそこから再生します。日が当たる場所で一か所に密集させておけば越冬できる確率が高まります。
花を咲かせる条件がよくわからない
ホテイアオイは夏に幽遠な紫色の花を咲かせます。
ということになっているのですが、長いこと育てているものの咲かせる条件が未だに分かりません。何度か咲かせた経験はあるのですが、何が良かったのかさっぱり分からず。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 花の咲かせやすさ …
- 産卵床としての使いやすさ …
アマゾンフロッグビット
小ぶりな葉が可愛い浮草
「アマゾン」という名前のおどろおどろしさとは違い、小ぶりで虎柄の葉が可愛い浮草。

アマフロの愛称でも知られています。フロッグビット(BIT)なのかフロッグピット(PIT)なのか曖昧で私は正解が分かりません。どちらでも意味が通りそうで売ってる側も結構バラバラ。
ホテイアオイと比べるとビジュアル的に控えめで高さもなく、他の水草と組み合わせても馴染みやすい見た目をしています。主役ははれませんが名わき役。
耐寒性のある浮草
真夏の直射日光に当たると色あせるという性質が商品説明として書かれれていることがあり、実際8月ぐらいはちょっと元気が無く見えたりします。それでも特に生育に問題は無く真夏にどんどん増えていきます。
秋を迎えて他の浮草の元気がなくなっていく中、しぶとく緑色の葉を絶やさないのもアマゾンフロッグビット。いかにも熱帯出身っぽいアマゾンの名を冠しているのに寒さに強く、ホテイアオイより高確率で冬を越せます。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 他の水草との馴染みやすさ …
オオサンショウモ
撥水性のある葉が特徴
言われてみれば山椒の葉に似ているような似ていないような。2つ折りになったような形の葉と、そこに生えた撥水性のある毛が特徴的な浮草です。

アマゾンフロッグビットよりさらに細かい葉で、こちらも他の水草と組み合わせやすい水草です。夏の厳しい暑さにはちょっと弱い印象。寒さにも弱く冬場はほぼ枯れてしまいますが、日向で他の水草と密集して育てていたりすると冬を越せる場合があります。
細かくて軽い浮草なので、大雨なので水があふれると外に漏れ出てしまう可能性があります。注意しましょう。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 葉っぱの撥水性 …
水中に漂うタイプの水草
水中に漂うタイプのメリットデメリット
簡単に増やせる
たぶん水草と聞けば多くの人はこのタイプを思い出すんじゃないかと思われる、水中に漂う細長い水草。都会の汚い用水路でもびっしり生えていたりするタフなやつも多いです。増やすのはかんたんです。
産卵床としては使いにくい
ホテイアオイと同じくこのタイプの水草も産卵床としての役割を果たしますが、浮草に比べたら扱いが面倒。いちいち水槽に手を突っ込んで回収しないといけないし、卵の取れ高も低い。
水質浄化とメダカの隠れ家として貢献するので、1種類は入れておいたほうが飼育しやすくなります。
マツモ
根っこが無いから扱いやすい
初心者におすすめの2種としてすでに紹介したマツモ。

もう一つの定番水草として知られるアナカリス(オオカナダモ)より繊細で和の雰囲気があるので、私は大好きな水草です。水質の変化で溶ける場合がある以外は丈夫な水草で、氷が張るような地域でも問題なく冬を越せます。冬場は葉を畳み水底に沈んで春を待ちます。
同じタイプのバリエーションとしてアナカリスやカボンバも紹介すべきところですが、やはりマツモの特徴である「根っこがない」というのは扱いやすく初心者でも安心。この1種の紹介のみにとどめます。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 繊細な和の雰囲気 …
水面ギリギリの土に植えるタイプの水草
水面ギリギリの土に植えるタイプのメリットデメリット
後ろに配置すると奥行が出る
日本の原種メダカであるミナミメダカの学名は「Oryzias latipes」。学名の意味は『稲の周りにいる足(鰭)の広い』とのこと(Wikipediaより)。
水田と深い関わりあいのある魚というわけです。それなら稲のように根元の部分が水に浸かっていて葉の部分が水上に出ているタイプの植物と相性がいいのは必然。このタイプの水草は背が高くなるものが多いので、ビオトープの奥に配置するとバランスよく見えます。

思わぬところから株が生えてきてしまう
このタイプの水草は地下茎を伸ばして株が増えるものが多くあります。
手入れせずに放っておくと、プランターの穴からランナーが通り抜けて、思いもしないところに根を張って株が増えることがあります。チェックと間引きが手間になります。
シラサギカヤツリ
常に花(のようなもの)が咲いている
水面からまっすぐに伸びた細長い葉と白い花が特徴的なシラサギカヤツリ。

花びらに見える白い部分は葉であり、花はその中心にあります。
春から晩秋まで次々と新しい花芽が伸びてくるので、メダカのオンシーズンは絶え間なく花が楽しめます。花そのものは枯れてしまっても花に見える白い葉は数週間程度長持ちするので、見た目上は花の開花が途切れません。
小さなポットで土に植えられた状態で売られていますが、とりあえずはそれをそのままビオトープに沈めればいいのでカンタンです。
分けつするから増やすのが簡単
稲と同じ分けつというかたちで株が増え、さらにクローバーのような地下茎でもどんどん株が広がります。増えた株をちぎって分割することで容易に増やしていけます。植え替えとか難しそうと身構えるかもしれませんが、適当なポットや植木鉢に赤玉土の小粒を入れてそこに株を植えるだけです。
枯れたように見えるけど越冬可能
冬は水上に出ている葉が茶色く枯れて死んだように見えますが、水面下の根や茎はしっかり残っていてかんたんに冬を超えられます。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 花の咲かせやすさ …
- 開花の途切れなさ …
ナガバオモダカ
「メダカが喜ぶ水草」として人気
ホームセンターの水草売場では「メダカが喜ぶ水草」というコピー文で売られているナガバオモダカ。名前の通り長くて丸みを帯びた葉っぱが垂直に立ち上がります。

これもポットに入れて売られている状態のまま水に沈めるだけ。
ビオトープ内で最も早く花を咲かせる
春先のかなり早い時期から白い花を咲かせます。

ビオトープで花を咲かせる水草は数あれど、春先の一番早い時期に花をつけるのがナガバオモダカ。早ければ3月中には花を咲かせ、それから数カ月間は新しい花の芽が次々に伸びてきては花を咲かせることを繰り返します。
ランナーを伸ばしてどんどん株が増える
ホテイアオイのようにランナーを伸ばして子株をつけ増えていくタイプ。放っておくと思いもよらぬ場所に根をはって定着してしまうので、気が付いたら抜くなどしておきましょう。

それ以外は管理が楽な水草です。抜いた子株は適当な土に植えておけばまたぐんぐん成長します。だから増やすのは超カンタン。1年で10倍ぐらいの株数になります。
冬は水中葉が緑色をたもったまま越冬する
冬場は水面上の葉が枯れてしまいますが、ロゼッタ状に広がる水中葉がずっと緑色を保ったまま冬越えできるので、寒い時期でもビオトープにいろどりを添えてくれます。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 花の咲かせやすさ …
- 葉っぱの高さ …
稲を植えることも可能だけど…
ビオトープで稲は育つ
稲っぽい水草を望むのなら、文字通り稲を植えたらいいのでは?
そう思い立って実際にやったことがあります。たまたま手元に稲の栽培キットがあったので。本来は「バケツで育てよう」という趣旨の栽培キットでした。
結果どうなったかというと、ちゃんと育ってお米を収穫できるところまでやり遂げることができました。これがそのときの様子です。

確かにお米の穂が実っていますがアンバランスですよね。
大きくなりすぎるからビオトープに入れるべきではない
玄関先の小さなビオトープにとって稲は大きすぎたのです。背も高くなりすぎた。長大な根っこを受け止め切れる土の量でもなかった。
鑑賞用の稲自体は存在するようなのですが、小さなものでも50センチと家庭のビオトープに植えるにはやはり背が高過ぎます。ビオトープ用にミニ稲みたいな品種があったら面白いし人気も出ると思うのですが。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 巨大化しやすさ …
土に植えて完全に沈めるタイプの水草
土に植えて完全に沈めるタイプのメリットデメリット
水中葉と水上葉が楽しめる
土に植えてかつ葉が完全に水中にあるタイプの水草。アクアリウムの経験がない人にとっては水草の中で一番馴染みのないタイプかもしれません。
葉が水中にあるといっても水中と水上どっちでも対応できる種類が多いので、あまり気にせず適当にすればいいです。水中で成長する水中葉、水面から上で成長する水上葉があり、それぞれ少し葉の形が異なります。
水中から水面に立ち上がって生えるので森のような景観を作り出すことができます。

土が必須なので手間がかかる
土に植わっているタイプなので難しそうに感じるかもしれませんが、まずはポットに入って売られている状態のものをそのまま沈めるだけで大丈夫。
生長して増えてくれば株分けや差し戻しなどの方法で増やすことができますが、かならず土が必要なのでポットと赤玉土などが都度必要になるのが手間です。

ウォーターバコパ
青くて小さなかわいい花をつける
肉厚の小さな葉がかわいいウォーターバコパ。

夏から秋にかけて小さな紫の花を咲かせます。

茎頂から2~3節下の目立たない場所につぼみを付け、たった一日で花が落ちてしまう意外と可憐な花。
差し戻しでどんどん増やせるので、かんたんに森の景観を作り出すことができます。
冬は水中葉で越冬する
冬場は水面上に出た葉が枯れてしまいますが、水面下にある葉は緑色を保って冬を越せます。
茎や肉厚の葉をちぎると、ミントとレモングラスを足したようないい香りがします。夏場はどんどん伸びるので、間引きがてら香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 花の咲かせやすさ …
- 香りのよさ …
グリーンロタラ
春に白くて小さな花をつける
春に小さくて白い花をつけるグリーンロタラ。

ウォータバコパと葉の形が似ているので一見すると見分けがつきにくいですが、花の形が全く異なります。これも差し戻しを繰り返せばモサモサの森にできます。
上の花が咲いた状態から2カ月ほど差し戻しを繰り返したのち、真夏を迎えたグリーンロタラがこちら。

水面から葉が溢れてモッサモサになりました。この間、肥料は一切与えていません。メダカの糞などがバクテリアの作用によって分解され生成された養分。それだけでここまで育ちます。
冬は水中葉をつけて越冬する
こちらもウォーターバコパと同じく越冬が可能です。水上の葉が枯れたように見えても、水面下の葉は生きています。
- 育てやすさ …
- 耐寒性 …
- 花の咲かせやすさ …
- 成長の旺盛さ …
ビオトープの水草について知っておきたいこと
ビオトープの水草について、周辺の豆知識を列挙します。
メダカ用の水草はホームセンターで買える
屋外園芸コーナーを狙おう
ペットショップやアクアリウムショップ、ホームセンターなど、メダカを取り扱っているお店であればメダカ用の水草も取り扱っています。
中でも最近はホームセンターでの品揃えが充実しています。もともと大規模な店舗であれば屋外の園芸コーナーがあるはずなので、その延長線上でメダカ用の水草コーナーが設置されています。近年はメダカブームの煽りを受け、どんどん売り場が拡張されている傾向。

ここまでで紹介した水草もすべてホームセンターで手に入れたものです。
一方、室内に置いた小さな容器で水草と魚を飼うアクアテリアというジャンルがあります。
これは屋内のスペースに売り場が展開されていることが多く、そこでも水草が売られています。いかにも屋内用という体裁で小さな水草が並べられていますが、暖かい季節であれば屋外環境に適用できるものがほとんど。屋外で育てればすぐに生長して増えるので、ここで安く買って増やすのもアリ。
販売期間は気温が高い時期のみ
ただしホームセンターでは販売期間が限定的。
早いところで4月ぐらいから売り場が開設されますが、夏の終わりぐらいには値下げが開始されて規模が縮小していきます。秋には葉が落ちた休眠株を捨て値で売ってたり。屋外飼育は四季の移り変わりと連動するので仕方がないですね。
葉が落ちていてもまた春を迎えれば芽吹いてくる水草がほとんどなので、秋はお得に水草を揃えられる絶好の機会だったりします。
もしかすると関西に限ったことかもしれませんが、ホームセンターで売られている水草のほとんどが京都の水生植物専門店である杜若園芸の製品。
ビオトープをやるなら実用的かつ親しみやすい内容のYouTubeも必見です。
夏場は増えすぎに注意する
ビオトープに様々なメリットをもたらす水草ですが、増えすぎてしまった場合は悪影響を及ぼす可能性があります。
増え過ぎるとメダカに悪影響を与える可能性が
水面を塞いでしまい水中への酸素供給を妨げてしまうことが悪影響のひとつ。水面を覆わずとも、日光を受けない夜間は水草が酸素を消費してしまいます。
ふたつめはメダカの行動範囲を狭めてしまう可能性があること。メダカは器用に避けて泳ぎますが、水草で埋め尽くされた水中は窮屈で成長スピードにも悪影響を与えます。
また、増えすぎた水草が枯れて腐ってしまうと水を汚す原因となります。時々ビオトープの中をチェックして、枯れてどろどろになった水草があれば除去する用意しましょう。

せっかく買ったのにもったいないと思うかもしれませんが、放っておいてもどんどん増えます。躊躇せず間引きして捨てましょう。
先ほども書きましたが、増えすぎた水草を捨てる際は自然下に流出しないよう気をつけてください。私はビオトープ横に放置してカラカラに乾燥させてから燃えるゴミに出しています。
水草はどんな土に植えたらいい?
土に根っこを張るタイプの水草は土に植えないといけません。どんな土が使えるでしょうか?
水生植物専用土が安心
まず水生植物専用の土というものが売られており、さしあたりこれを選んでおくと間違いありません。
今までこの土でウォーターバコパから姫睡蓮までいろいろな水草を育ててきましたが、特に問題なく成長して花を咲かせることもできました。栄養分が少ないのでメダカに悪影響を与えることもありません。
メダカ用として売られているソイルも水草の土として使えます。
赤玉土小粒が安くて万能
ただ実際のところ、赤玉土の「小粒」さえあれば十分。これだけであらゆる水草が育てられます。
値段も5リットル200円台という低価格で手に入るから超リーズナブル。そしてこの赤玉土小粒はメダカビオトープの底土としても定番。余っても無駄になりません。
睡蓮などは赤玉土を練って泥状にする過程が必須とされていることもありますが、汚れるし面倒なので私は一度もその作業をしたことがありません。粒のままでもちゃんと開花までもっていけます。
ただ、赤玉土は養分を一切含まない土であるということは留意しておいたほうがいいでしょう。また、植物の肥料として欠かせないリン酸を吸着して植物が利用することができない状態にしてしまうという性質も持っています。
とにかく植物を元気に育てたい、植物をメインにしたビオトープにしたい。そのような目的においてベストな選択とは言えないかもしれません。植物がメインなら田んぼの土、荒木田土などのほうが生育が良いと思われます。
とはいえ赤玉土だと目に見えて植物の育ちが悪いということも経験上ありません。同条件で他の土と比較すれば差が出るのでしょうが、通常は問題なく使えます。
苗用の小さなポットに植えるのがおすすめ
水草はビオトープの底に敷いた赤玉土などの底床に直接水草を植えることもできます。しかし管理の容易さを考慮すると苗用の小さなポットに植えるのがおすすめです。

底床だと一度植え付けたら水草を動かしにくいですが、ポットであれば植物の配置変更も自由自在。また、ポットの大きさ以上には生え広がりにくいので、ある程度は生長をコントロールできます。
ホームセンターの園芸売場であればだいたい10個セット100円台で売ってるのでリーズナブル。
植え替え直後はポットが丸見えで見映えが悪いのですが、気温が上がって水草が繁り始めると気にならなくなります。上のポットが映ってる写真から2カ月足らずでこのとおり。

肥料を与える必要はない
肥料成分は自然に供給される
植物だから定期的に肥料をやらなければいけないのでは?めんどくさそう…
安心してください。肥料は勝手に供給されます。肥料の主な原料はメダカの糞。バクテリアの働きで糞が分解されて肥料となります。
土に植えるタイプの水草は追加で肥料をやれば確実に生長が旺盛になりますが、水質の安定や浄化を期待するなら基本は不要で構いません。肥料が水を汚すこともあるので下手なことはしないほうがメダカにとっても安全。
さきほども掲載したこの水草もりもりのビオトープ、確実に花を咲かせたい睡蓮以外は肥料を一切与えていません。それでも夏にはこんなに繁ります。

肥料を使うならマグァンプK中粒がおすすめ
睡蓮の花を確実に咲かせたいと言う目的なら肥料は必要です。
その際はゆっくり効いて水を汚しにくい緩効性の肥料を使うと安心。私はビオトープに睡蓮も入れていますが、植え替えの際にこのマグァンプという緩効性肥料を土に混ぜ込んで使っています。
元肥と呼ばれる植え付け時に使うタイプの肥料なので、しっかり土に混ぜ込んで使ってください。表面にパラパラ撒く程度ではほとんど意味がありません。植物の根から出る酸、根酸で溶けだす成分が多く含まれるので、根っこに直接あたっても大丈夫。
多くの水草は冬を超えられる
夏場は青々としていた水草も気温が下がるにつれ元気がなくなり、12月に入るぐらいになると枯れる葉っぱも出てきます。水面が凍るような寒い日もあるでしょう。

ビオトープの水草はこのままで大丈夫なのでしょうか?冬を超えられるのでしょうか?
関東以南の平野部であればたぶん越冬可能
その年の寒さやお住まいの地域によって条件が違うのではっきり言い切れませんが、水面下に根っこが沈んでいるタイプの水草であれば基本的にそのまま放置で大丈夫です。関東以南の平野部であれば水面が凍る日もそう多くないので冬を超えられる水草は多いはず。
水面の上に出ている葉は枯れたり溶けたり赤茶けた色に変わったりしますが、水面下で小さな葉をつけたまま休眠状態になる水草がほとんど。株元に少しでも緑色の部分が残っていれば生きていると考えていいでしょう。

冬を超えて生き残った水草は、春に植え替えや株分けをすることでまた元気に生長してくれます。つまり翌年は再利用できるわけです。毎年新たに買いたす必要はありません。
ほとんどの浮草は寒さに弱い
ホテイアオイなどの浮草は一般的に寒さに弱く、冬を超えられず枯れてしまうものが多い。それでもわずかに緑色の部分残して春を迎えれば、そこから再生させていくことができます。西日本の平地にある我が家のビオトープではなんとかホテイアオイの一部が生き残って春にまた再生します。もう何年も買い足していません。

どんな水草にせよ、枯れてドロドロになってしまっては水を汚す原因になるので、その部分は切り取るなどして取り除いておいた方がいいでしょう。
川や池で採取した水草を使っても大丈夫?
例えばアナカリス、つまりオオカナダモ。これはそこらじゅうの川や池に生えています。ドブみたいな川にも生えてます。
外来種ではあるものの特定外来生物には指定されていないので、持って帰ってビオトープに入れることは法律上問題ありません。無料で取り放題です。
付着物には注意が必要
注意したいのは、雑菌や寄生虫、モノアラガイなどのスネール類(小さな貝類)、水生昆虫、謎の生物の卵などが付いている可能性があること。
可能性と書きましたがほぼ間違いなく何かがついてます。ちょっと洗ったぐらいでは落ちません。それがビオトープに悪影響を及ぼす可能性があるということは頭に入れておく必要があります。いったん入り込んでしまった小さな生物類の除去は極めて困難です。
水草についている貝類を除去できるとされている薬品があるので、気になるならそれを使ってみるのもいいでしょう。農薬も落とせるとされています。
この手の薬品、成分はアルカリ性のいわゆる消石灰らしく、これを使うと水に油膜が浮きます。アルカリ成分で何かしらの成分が溶け落ちているのは分かります。果たしてこれが汚れなのか、貝類や水草の細胞組織が溶けたものなのかは分かりません。農薬が落ちているのかも正直言って半信半疑。スネール類が一網打尽に出来るかというと…自分は無理でした。

なので基本的に水草はお店で買った方が良いと思います。ちゃんと無農薬と銘打った水草が売られているはず。それでもスネールとかはついてきたりするんですが…
採ってはいけない水草もある
水草の中には特定外来生物に指定されて栽培・保管・運搬が禁止されているものもあります。かつてウォーターレタスとして売られていたボタンウキクサや、近年日本各地で繁殖しているのが見つかって「地球上で最悪の侵略的植物」と呼ばれているナガエツルノゲイトウなどです。許可なくこれらを持って帰ると最悪の場合は罪に問われる可能性があることは知っておくべき。
もちろん貴重な天然記念物も採取してはいけませんし、採取が禁止されているエリアがあるかもしれません。そうでなくても数が少ないものを持って帰るのは十分に慎重にならなくてはいけない。
いずれにせよ野生の水草を利用する場合はしっかり知識をつけ、必要な情報を仕入れてからにしましょう。
好きな水草選んで自分だけのビオトープを
ここで紹介した以外にも、ビオトープに使える水草はたくさん。
まずはカンタンなものから始めてみて、徐々にステップアップしていけばいいのではないでしょうか。例えば姫睡蓮の花を開花させることができると達成感と満足感があります。
ビオトープは、メダカの飼育と園芸が同時に楽しめる飼育環境。
メダカの繁殖に慣れれば新しいメダカを買い足さずとも数十匹百匹単位で増やしていくことができます。水草一も回買えばどんどん増やしていけるのでほとんど買い足す必要がありません。軌道に乗ればお金もかからず飼育に必要な場所もコンパクトなので、現代の生活事情にあった趣味だと思います。
メダカの飼育に慣れたら水草の飼育にも挑戦してみてください。きっと新しい扉が開きます。四季を通して日々の楽しみが増えます。生活に張りがでます。花が咲く幸せを味わえます。
屋外でのメダカ飼育全般についてはこちらに詳しくまとめています。ぜひご参考に。